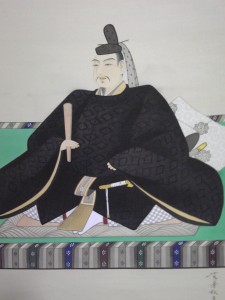今日から寒波が南下してくる為に、とても寒くなり積雪もあるようです。
今日から寒波が南下してくる為に、とても寒くなり積雪もあるようです。
北陸富山のお正月は、暖かく天候に恵まれたこともあり、何処に行っても賑わいを見せていました。
少しだけ視野を広げてみるとアメリカでは過去20年で『最強寒波』の襲来だという!
昨日のNHKニュースで、-15℃の市街を歩く日本人カップルが、「寒すぎて頬っぺが痛いです」「もうホテルに帰ります」などとも言っていた。(寒)
アメリカ全土で最も低気温は、ミネソタ州クレーンレイクの-38℃
モンタナ州カマータウンでは、体感温度-53℃までさげた。とも、ありました。正に凄まじい寒波です!!
日本では温暖化が、未だに叫ばれてはいますが、一転!そうではないと感じているのは僕だけではないと思います。世界規模で起こっている『最強〇〇』〇〇に入るのは寒波であったり台風であったりと、これ以上〇〇は増えてほしくはありません。
世界規模で起こっている異常気象は、以前より起こっている太陽の影響をもろに受けているからであり太陽系規模まで広げてみて見る必要があるのではないかと思います!
たとえば、以前に太陽の黒点が消えていた時期があったり、一転して活発に活動し大きなフレアを放出したりと陰陽の高低が激しくて
地球上への影響は計り知れません。
今回、日本列島に南下してくる寒波というか寒気はアメリカに匹敵するものではないので今のところは安心ですが、日本に『最強〇〇』がやってこない!とは限らなく、やってこない事を祈るしかないのが現状であると考えます。
『そんなもん大丈夫、大丈夫』と何も考えず!ではなく、『どう対処するかを予測したうえで、大丈夫だ!』と言えるようにしておきたいと一家の長として強く思う次第です。