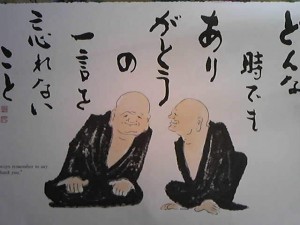昨日と本日の両日は田祭りで、地区内を夜高行燈が曳き廻されます。6月初旬!田植えがすべて終わった人々が、久しぶりの休みを取る意味の「休む事」から「やすんごと」「やすごと」といわれるこの時期に行われるお祭りであり、神事です。
昨日と本日の両日は田祭りで、地区内を夜高行燈が曳き廻されます。6月初旬!田植えがすべて終わった人々が、久しぶりの休みを取る意味の「休む事」から「やすんごと」「やすごと」といわれるこの時期に行われるお祭りであり、神事です。
この時期に各家では、笹の葉や茗荷の葉で包んだ押し寿司をたくさん作り「やすんごと」「やすごと」には何もしない。という暗黙の了解があったものだそうです。お母さん方も完全に「やすごと」だったんですね!?いつもありがとうございます。(拝)
起源は南砺市福野町の開町の時に伊勢神宮より分霊され、行燈でお迎えしたのが始まりとか。富山県砺波市・南砺市の福野夜高祭りをはじめ、砺波・庄川夜高祭り、小矢部市津沢夜高祭りが盛大に行われ、大変な賑わいを見せています。
北海道沼田町でも行なわれていて、ルーツである小矢部市津沢出身の方々との嬉しくも懐かしい交流が現在も続いています。以前にはNHK朝ドラ「すずらん」で有名でした。覚えています!^^
写真の夜高行燈は本日!豊年満作・五穀豊穣を祈念しながら地区内を曳き廻し、終了後に取り壊されます。福野、砺波、庄川、津沢の夜高行燈は「ケンカ」といわれる行燈のぶつけ合いが勇壮に行われ、盛り上がりを見せています。
このすばらしい神事が永きにわたって続いていくことをこころより願っています。